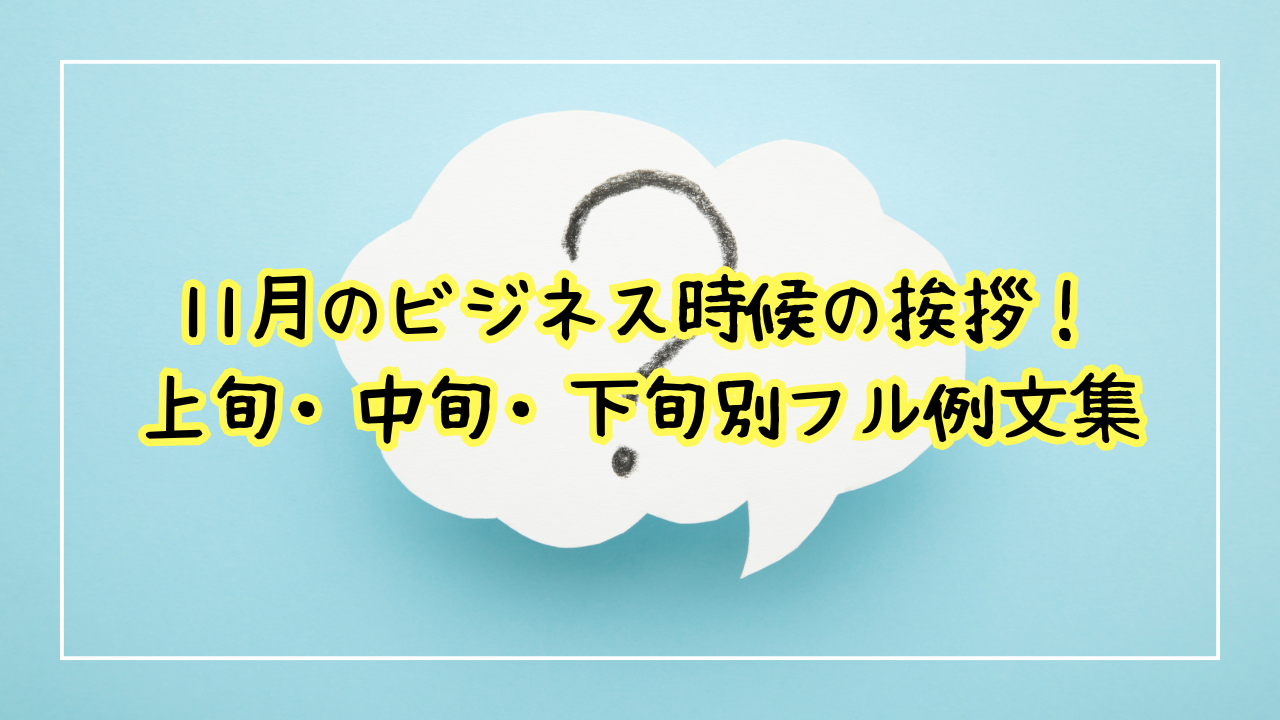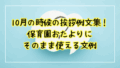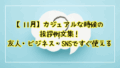11月は、秋の深まりと冬の訪れを同時に感じられる季節です。
ビジネスシーンにおいては、こうした季節感を挨拶文に取り入れることで、相手への丁寧な気配りや礼儀を示すことができます。
本記事では、「11月の時候の挨拶」をテーマに、上旬・中旬・下旬ごとにふさわしいフレーズや、取引先・社内・初めての相手に向けたシーン別の活用例を豊富に紹介します。
漢語調の定型表現から、柔らかい自然描写を交えたカジュアルな挨拶まで幅広く網羅しているので、あらゆる場面で使える一文がきっと見つかるはずです。
さらに、本文に入る前にそのまま使えるフルバージョン例文も多数掲載。
形式的な挨拶文に終わらせず、相手に好印象を残すためのコツも解説しています。
寒さが増す11月、心のこもった挨拶で信頼関係を深めていきましょう。
11月の時候の挨拶とは?ビジネスでの役割と基本マナー
11月は秋から冬への変わり目で、ビジネス文書にも独特の季節感を取り入れることができます。
ここでは、そもそも時候の挨拶とは何か、そして11月ならではの特徴や使い方の基本を解説します。
まずは全体像をつかんでおくと、挨拶文を書くときに迷いが減ります。
時候の挨拶の意味と使われる場面
時候の挨拶とは、季節の移ろいを感じさせる言葉を手紙やメールの冒頭に添える慣習です。
日本では古くから使われてきた文化で、特にビジネス文書では礼儀や心配りを示す役割を持ちます。
「拝啓 向寒の候」などが典型的な表現です。
取引先への正式な手紙や、フォーマルなメールで特によく用いられます。
| 場面 | 使用例 |
|---|---|
| 取引先への文書 | 拝啓 立冬の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 |
| 社内メール | 紅葉が見頃を迎えましたね。皆さまいかがお過ごしでしょうか。 |
| 初めての相手 | 晩秋の折、初めてご連絡差し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
11月に使われる代表的な季語と特徴
11月の季語には、「紅葉」「晩秋」「立冬」「向寒」などがあります。
これらの言葉は秋の名残と冬の訪れを同時に感じさせる点が特徴です。
ビジネス文書では、あまりに気候とズレた表現を避けることが大切です。
たとえば暖かい日が続いているのに「厳冬の候」と書くと違和感が出てしまいます。
無難に使える言葉を表にまとめると次の通りです。
| 季語 | 意味・ニュアンス | 使用時期 |
|---|---|---|
| 晩秋 | 秋の終わりを表す | 11月上旬まで |
| 立冬 | 暦の上で冬が始まる | 11月7日頃〜 |
| 向寒 | 寒さが近づく様子 | 11月全般で使える |
| 初霜 | 初めて霜が降りる季節 | 11月上旬〜中旬 |
11月に使えるビジネス挨拶文例【全般】
11月全体を通して使える挨拶文は、幅広い場面で役立ちます。
ここでは、漢語調の定型表現と、やや柔らかい口語調の表現に分けて例文をご紹介します。
シーンに応じて組み合わせることで、より自然で丁寧な印象を与えられます。
漢語調(〜の候・〜のみぎり)の定型表現
漢語調の挨拶はフォーマルさを重視したいときに最適です。
格式を保ちつつも、相手を気遣う文言を添えることで文章に温かみが生まれます。
| 挨拶文例 | 使える場面 |
|---|---|
| 拝啓 向寒の候、貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 | 取引先への正式な文書 |
| 立冬のみぎり、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 | 年末が近い時期の挨拶 |
| 晩秋の候、皆様にはお変わりなくご清祥のことと存じます。 | 社外メール全般 |
| 残菊の候、貴社のご繁栄を衷心よりお祈り申し上げます。 | フォーマルな依頼文・案内文 |
柔らかい口語調・自然描写を取り入れた表現
ややカジュアルな相手や、親しみを持たせたいメールでは自然の情景を描写した挨拶が役立ちます。
11月は紅葉や枯葉、日暮れの早さなど、誰もが共感できるキーワードが多いのが特徴です。
| 挨拶文例 | 使える場面 |
|---|---|
| 紅葉も見頃を迎え、はなやかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 | 社内メールや親しい取引先 |
| 日が暮れるのが早くなり、冬の足音を感じる頃となりました。 | 年末を意識したビジネス文書 |
| 枯葉舞う季節となりましたが、お健やかにお過ごしのことと存じます。 | 少しかしこまった挨拶メール |
フォーマルさが必要なときは漢語調、親しみを演出したいときは自然描写を選ぶと失敗がありません。
同じ相手に送る場合でも、場面によって使い分けることが重要です。
11月上旬のビジネス挨拶例文
11月上旬は、秋の深まりを感じながらも冬の入口を意識する時期です。
紅葉や秋晴れといった明るい表現を使いつつ、少しずつ寒さを気遣う言葉を加えるのがコツです。
ここでは、汎用性の高い例文と、結びに工夫を加えたフルバージョン例文をご紹介します。
秋の深まりを表す挨拶文例
11月上旬は、紅葉や晩秋をキーワードにした挨拶が自然です。
堅めの場面でも使える漢語調から、やや柔らかい表現まで揃えました。
| 挨拶文例 | 使える場面 |
|---|---|
| 拝啓 晩秋の折、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 | 取引先への正式な文書 |
| 秋晴れの日が続いておりますが、皆様にはお健やかにお過ごしでしょうか。 | 社内メールや親しい関係の相手 |
| 枯葉舞う季節となりましたが、お変わりなくお元気でいらっしゃいますか。 | ややフォーマルな挨拶メール |
結びの一文で差をつけるコツ
挨拶文の後に続ける「結び文」で印象は大きく変わります。
11月上旬なら秋の余韻を残しつつ冬支度を意識する言葉がぴったりです。
| 結びの例文 | ニュアンス |
|---|---|
| 年末に向けてご多忙のことと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。 | 体調を気遣い、年末を意識 |
| 朝夕の冷え込みも増しておりますので、くれぐれもご健康にご留意ください。 | 寒さへの配慮を示す |
| 晩秋の候、皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 | 丁寧かつ汎用性が高い |
以下に、冒頭から結びまで揃ったフルバージョンの挨拶文例を示します。
拝啓 晩秋の折、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
秋晴れの日が続き、紅葉も見頃を迎えておりますが、皆様にはお健やかにお過ごしでしょうか。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、【本文】。
年末に向けご多忙のことと存じますが、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。
敬具
11月中旬のビジネス挨拶例文
11月中旬は、立冬を過ぎて本格的に冬の気配を感じる時期です。
寒さを意識した言葉を取り入れつつ、紅葉や秋の余韻を感じさせる表現を盛り込むと自然です。
ここでは、定型挨拶と結びを含めた実用的な例文をご紹介します。
立冬を過ぎた季節感を表す挨拶文例
11月中旬は暦の上で冬に入る「立冬」の頃であり、夜の冷え込みを描写すると季節感が出ます。
堅めの漢語調と柔らかい描写文の両方を使い分けられると便利です。
| 挨拶文例 | 使える場面 |
|---|---|
| 拝啓 立冬の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 | 取引先やフォーマルな挨拶状 |
| 暦の上では冬を迎えましたが、なお秋の名残も感じられる頃ですね。 | 親しい相手へのメール |
| 夜の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 | 社内文書や軽めの挨拶 |
相手を気遣う結びの挨拶
中旬は気温の変化が大きいため、体調を気遣う言葉を添えると安心感を与えられます。
寒暖差を踏まえた結びを入れると、より実用的です。
| 結びの例文 | ニュアンス |
|---|---|
| 紅葉の美しい季節、皆様のご発展を心よりお祈り申し上げます。 | 秋らしさを強調しつつ丁寧に締める |
| 冷え込みが増しておりますので、どうぞお体にお気を付けくださいませ。 | 健康への配慮を伝える |
| 年末に向けご多忙のことと存じますが、ご自愛くださいますようお願い申し上げます。 | 仕事の繁忙期を気遣う |
以下は、冒頭から結びまで揃えたフルバージョン例文です。
拝啓 立冬の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
木々の彩りもいよいよ深まり、秋の名残を惜しむ今日この頃ですが、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、【本文】。
寒さに向かう折、どうぞご健康には十分ご留意くださいませ。
敬具
11月下旬のビジネス挨拶例文
11月下旬は、冬の到来を強く意識させる時期です。
小雪や木枯らしといった季語を取り入れると、季節感が一気に増します。
また年末を見据えた言葉を添えることで、気配りのあるビジネス文に仕上がります。
冬の訪れを意識した挨拶文例
寒さを前面に出した表現や、秋を惜しむ言葉がよく使われます。
「小雪」「惜秋」「木枯らし」などのキーワードを押さえておくと便利です。
| 挨拶文例 | 使える場面 |
|---|---|
| 拝啓 小雪の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 | フォーマルな取引先文書 |
| 惜秋の折、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 | 秋の終わりを意識した挨拶 |
| 木枯らしの吹く季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 | やや柔らかい表現のビジネスメール |
年末を見据えた結びの挨拶
11月下旬は、年の瀬が近づくことを意識した言葉を添えるのが効果的です。
「師走に向けての気遣い」を結びに加えると、より気の利いた文になります。
| 結びの例文 | ニュアンス |
|---|---|
| 年末に向け何かとご多忙のことと存じますが、ご自愛専一にてお過ごしください。 | 繁忙期を労う表現 |
| 寒さも厳しくなってまいりました。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 | 冷え込みを意識した結び |
| 本年も残すところわずかとなりましたが、変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。 | 年末らしい丁寧な挨拶 |
以下にフルバージョン例文をご紹介します。
拝啓 小雪の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
木々の葉もすっかり落ち、冬の足音が間近に感じられる頃となりました。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、【本文】。
年末に向けご多用のことと存じますが、どうぞお体を大切になさってください。
敬具
シーン別・すぐ使える11月の挨拶文例集
同じ11月でも、送る相手やシーンによって適切な挨拶文は異なります。
ここでは、取引先・社内・久しぶりに連絡する相手など、よくあるシーンごとに実用的な例文をまとめました。
場面に応じた表現を選ぶことで、相手への印象がぐっと良くなります。
取引先へのフォーマルな挨拶
取引先には、礼儀を意識した漢語調の定型文が基本です。
短くてもきちんとした印象を与える表現を選びましょう。
| フル例文 | ポイント |
|---|---|
| 拝啓 向寒の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、【本文】。 年末に向けご多忙のことと存じますが、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 敬具 |
堅い挨拶文で信頼感を与える |
社内や親しい相手へのカジュアルな挨拶
社内や親しい取引先には、やわらかい自然描写を取り入れると温かみが出ます。
短いフレーズでも十分に効果があります。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 紅葉が美しい季節になりましたね。皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。 | 社内メールや軽い連絡の冒頭 |
| 日が暮れるのが早くなり、冬の訪れを感じます。どうぞ温かくしてお過ごしください。 | 親しい取引先へのメール |
初めて・久しぶりの相手に送る挨拶
初めての相手や久しぶりにやり取りする相手には、堅さと気遣いを兼ね備えた挨拶が無難です。
「初霜」「晩秋」などの季語を盛り込むと、手紙らしい趣が加わります。
| フル例文 | ポイント |
|---|---|
| 拝啓 晩秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。
久しくご無沙汰いたしましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。 平素は何かとお世話になり、誠にありがとうございます。 さて、【本文】。 寒さが厳しくなってまいります折、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。 敬具 |
再会や新規取引への丁寧な第一歩になる |
11月の時候の挨拶を書くときの注意点
11月の挨拶文は、相手や地域、文書の種類によって表現を調整することが大切です。
ちょっとした工夫で、形式的な文章もぐっと相手に伝わるものになります。
ここでは、注意しておきたい3つのポイントを解説します。
相手との関係性に応じた使い分け
取引先や目上の方には漢語調の定型表現を、社内や親しい関係には自然描写を使うのが基本です。
たとえば、初めての相手に「紅葉がきれいですね」と書くと軽すぎる印象になります。
フォーマルとカジュアルのバランスを意識して選びましょう。
| シーン | 適した表現 |
|---|---|
| 初めての取引先 | 拝啓 向寒の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 社内メール | 朝晩の冷え込みが増してきましたが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。 |
地域や気候に合わせる工夫
11月といっても、北海道では初雪が降る頃、本州では紅葉が見頃、九州ではまだ秋晴れの日も多いなど差があります。
気候に合わない表現は違和感を与えるので、相手の地域を意識するとより好印象です。
「こちらでは初霜が降りましたが、そちらはいかがでしょうか」など、ひとこと添えると丁寧です。
結び文で好印象を与える方法
挨拶の最後に添える結び文は、相手への配慮が最も表れる部分です。
11月なら健康や年末の繁忙を意識した言葉を入れると安心感があります。
| 結び文例 | ニュアンス |
|---|---|
| 寒さに向かう折、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 | 冷え込みへの配慮 |
| 年末に向けご多用と存じますが、どうぞご自愛くださいませ。 | 仕事の忙しさを気遣う |
| 冬支度の折、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 | フォーマルな結び |
まとめ|11月のビジネス時候の挨拶で信頼関係を深める
11月は、秋と冬が入り混じる季節だからこそ、挨拶文にも幅広い表現が使えます。
紅葉や晩秋を表す言葉から、小雪や木枯らしといった冬を意識する表現まで、状況に合わせて選ぶことが重要です。
形式的になりがちなビジネス文書でも、結びに気遣いのひと言を添えるだけで、相手に温かさを伝えられます。
| 押さえておきたいポイント | 具体例 |
|---|---|
| フォーマルには漢語調 | 拝啓 向寒の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 親しい相手には柔らかい表現 | 紅葉も色づき、秋の深まりを感じる頃ですね。 |
| 地域や気候に合わせる | こちらでは初霜を観測しましたが、そちらはいかがでしょうか。 |
| 結びで相手を気遣う | 年末に向けご多忙のことと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。 |
11月の挨拶文は、相手への思いやりを言葉に変えるツールです。
定型表現にひと工夫を加えるだけで、相手に与える印象は大きく変わります。
ぜひ本記事の例文を参考に、信頼関係を深める挨拶文を作成してみてください。